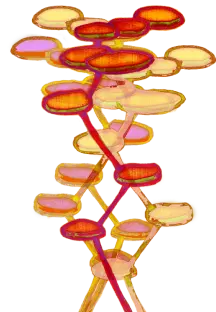11月30日、秋田市のにぎわい交流館AUにて「ソウゾウの森大会議2024」が開催されました。
一年の締めくくりということでその内容も盛り沢山だった大会議。2回に分けてその様子をお届けします。
玄関を開けて入ってくる冷たい空気に思わず「さむっ」と漏れた11月末の土曜日。今年のソウゾウの森会議を締めくくる「ソウゾウの森”大”会議2024」のため、秋田市へと向かう。
今年のソウゾウの森会議は、5月の「はじめる、ソウゾウの10年」でキックオフし、「湧き出る多様性」、「失敗から学ぶ」、「家〜私の暮らしをつくる」、「だれしもが活躍できるように」とさまざまなテーマで8月を除いて毎月開催されてきた。年に一度の “大会議” は、今年の会議を彩った地域主催者や参加者、ゲストとこの “森” に足を踏み入れた人たちが一同に会する場。各地で開催された会議を通じて出会った人たちと再会するのも楽しみだ。少し早いけれど、今年を振り返り来年何をしようかと想像するのに絶好の機会になりそうだという期待をもって、会場に入る。

古さからの転換
今年の集大成であるソウゾウの森大会議2024。各回の地域主催者、これまでのソウゾウの森会議参加者、そして今回初めて参加する人など総勢約80名が参加した。各会議を彩ったビジュアルがバナーとなって垂れ下がり華やかに会場を演出している。
冒頭、COI-NEXT 秋田拠点(通称ソウゾウの森)のプロジェクトリーダーを務める、秋田県立大学の高田克彦先生から開会の挨拶がある。2024年度より、国立研究開発法人科学技術復興機構(JST)から最長10年間の支援を受けながら、秋田の森林資源を活かした新たな価値を生み出す研究開発や取組を推進する本プロジェクト。JSTから期待されていることは「人、大学、社会の古さからの転換」と、高田先生が力強く語る。

続いて、国際教養大学の工藤尚悟先生から、ソウゾウの森会議について改めて説明がある。ソウゾウの森は、「森と木材」「森と空間」「森とまち」「森と技」そして「森と人」の5つの研究開発課題から成り、そのうちの「森と人」にソウゾウの森会議は紐づいている。各課題で生まれる研究成果をどう社会に実装し、変化につなげていくか。その可能性を広げる”人”が集うのがソウゾウの森会議という場であるとのこと。そして、ソウゾウの森が取り組む「森の価値変換」をしていった先には「自律した豊かさの実現」という大きなビジョンがある。

10年と聞くととても長く感じる。しかし、このタイミングで変化を起こさなければ、私たちが享受している自然の豊かさや地域のつながりは次世代に受け継がれることなく失われてしまうかもしれない。どう変化を起こすか、それを続けられるか?ソウゾウの森はその問いに答えるためのプラットフォームであり、挑戦者は私たち自身なのだ。
誰もが初心者
イントロダクションを終えて、壮大なビジョンを持つプロジェクトだということはよくわかった。でもどこから始めたらいいだろうか?その問いに答えるのが今回のテーマ「混ざりあう森」。人やアイデアが混ざりあう。その前の準備として用意されたアイスブレイク、その名も「ミニ異言語脱出ゲーム」が始まる。
ファシリテーターを務めるのは一般社団法人異言語Lab. 代表理事の菊永ふみさん。自身もろう者である菊永さんはゲームや体感型コンテンツを通し、ろう者と聴者をつなぐ体験を創出をしている。今回は各所で話題を集めている「異言語脱出ゲーム」をアイスブレイク用にアレンジして体験するとのこと。

4人1グループとなりアイスブレイクがスタート。4人のうち3人がそれぞれ配られたお題を説明し、残りの1人が何を伝えようとしているのかを考えるゲーム。ただし、ゲーム中のコミュニケーションは言葉や音を使ってはならない。お題だけでなくルールまでも身振り手振りで伝え、共通認識をつくる必要がある。
3人にはそれぞれ動物や家具の画像、ある手話の動きを説明された文言、図形により表現された顔の3つのお題が記された紙が手渡される。1つ目の画像は芋虫。手を使って尺取虫の動きを表現し、なんとか伝えることができた。続く手話の動きはこめかみの横でグーを作り、その手を上に押し上げながら開くという指示。受け手のシートには手話の動きが何を意味しているか、いくつかの選択肢があったそうで、その中から「忘れる」という意味だと推察したとのこと。
そして、最も難しく面白かったのは最後のお題。渡された紙には丸や四角、星型などで作られた福笑いのような顔が描かれているのだが、実は3人のうち1人だけ色や形が異なっているという間違い探しのゲーム。数字や色など伝えるべき情報が多いと、どこを伝えるべきか、相手がどこを伝えているかを汲み取るのが難しい。図形で作られた顔は、頭の先の帽子の上に丸が乗っているか否かや、顎の部分の色が違うなど、どう伝えればいいのか迷うものも多かった。振り返って考えると、相手の理解度を推し量りながら一つずつ丁寧に伝えるというのが最善の方法だったように感じる。




普段当たり前に使っている言語を離れてのコミュニケーション。言うなれば誰もが初心者である環境下では、相手の表情をより読み取ろうとしたり、目を見て伝えようとしたりすることで、お互い伝えよう、理解しようという気持ちが働く。言葉で「どんなアイデアも大歓迎!」と言われるより、発言や気持ちの共有がしやすくなった気がした。
人の数だけ広がるソウゾウの輪
アイスブレイクで場が和んだあと、今年ソウゾウの森会議を主催した5名の地域主催者によるパネルディスカッションが始まる。ファシリテーターは株式会社Q0の花岡竜樹さん。

それぞれから各回会議の振り返りがあったのち、話題はソウゾウの森会議の特徴に移る。
第12回の会場となった、秋田市の複合施設アトレデルタを運営する株式会社アウトクロップ代表取締役の栗原エミルさんは「講演の登壇者やゲストが固定化してきていると感じる秋田で、ソウゾウの森会議は知らなかったプレイヤーと出会える機会となっている」と語る。地域やテーマだけでなく、この場に集う参加者自体もこの会議の魅力になっていることが分かる。
大館を拠点に空き家活用や移住者支援を行う、NPO法人あき活Lab理事長の三澤雄太さんからも、「テーマをきっかけに今まで関わりが少なかった人を誘う機会になった」と、地域主催者としての観点でもコメントがある。「ソウゾウの森会議があるから来ない?」と声をかけられたり、「一緒にこのテーマについて考えてみない?」と誘いやすくなるのは想像に容易い。
輪の広がりは秋田県内の交流に留まらない。各回の開催地域やテーマに惹かれて参加する県外からの参加者が一定数いるのも特徴の一つだが、秋田市南通りの複合施設、ヤマキウ南倉庫の運営を行う株式会社See Visionsの山本美雪子さんは「県外から来た参加者の方が翌日他のイベントに参加してくださったり、地域の事業者を訪ねたりということもあった」とコメント。彼、彼女らにとって、会議に参加するだけでなく、地域主催者や参加者からの紹介を受けて地元の商店に立ち寄ったり、その時期ちょうど開催されていたイベントに参加するなども魅力的な体験になるだろう。地域、地域主催者、参加者の数だけその輪が広がったと考えるとその影響は大きい。
各回ユニークなテーマがあり、それに惹かれて参加する人たちが、会議を通じて深い体験や対話を経験する。さらに、前述のコメントにあったように、会議としてはデザインしていなかった発展も既に生まれてきていることが登壇者たちの感想から伝わってくる。意図的に植えた木々だけでなく、たまたま吹いた風や行き交う動物が種子を運び、あちこちに新しい芽を芽吹かせる。ソウゾウの森会議を通じて、森が育つようにいろいろな取り組みが生まれてくるのだろうと感じた。

「自律した豊かさ」とは
話題は何気ない日常や当たり前に存在する営みへと移っていく。
ネガティブな話題が多く、閉塞感が漂う秋田ではあるが、秋田市文化創造館ディレクターの芦立さやかさんは、よく隣のおばあちゃんから「たくさん育てちゃったから」と野菜をもらうエピソードをあげ、「助け合うという気持ちが強い」という点を指摘する。当たり前に秋田で享受していることが、実はとても豊かなことだと気づかされる。
また、「木々を間伐することで山を維持し次世代に残すように、人間関係も程よい距離感でメンテナンスし、繋いでいくことが大事」と付け足すのは、株式会社ヘラルボニー岩手事業部シニアマネージャーの木村芳兼さん。昔からある地域の慣習や組織の文化は、時に人が地域を出ていくきっかけになってしまうが、今回のアイスブレイクのように互いに歩み寄り理解する機会を持つことができれば、違いを乗り越えて課題に立ち向かうチームをつくることだってできる。「早く行きたければ一人で行け、遠くへ行きたければみんなで行け」というアフリカのことわざを思い出す。肩書きや年代で人々を分けず、一人の人としてお互いに理解、対話をする必要があると改めて思う。
会の中盤、栗原さんが「『ソウゾウの森会議って何?』と人から聞かれたとき、皆さんどう説明していますか?」と会場に問いかける。言われてみると確かにわかりやすく説明するのは難しい。
ソウゾウの森会議は、参加者の選択を尊重する。社会課題の解決を志すのか、個人の思いを重視するのか。都市をフィールドにするのか、地域に根ざして活動するのか。個人事業主なのか、法人化するのか、はたまた社内起業なのか。何かをソウゾウする中でとる選択について優劣があるとは考えない。よく言えば懐が深く柔らかい、でも反ってわかりづらい、説明しづらいというのも理解できる。
唯一示されているのは、冒頭工藤先生から紹介のあった「自律した豊かさの実現」というビジョン。これには、他人の決めたものさしで地域や個人の豊かさを測るのではなく、私たち自身にとって豊かさとは何か?という問いについて考え続けていくという姿勢が表現されている。秋田から、地域から、「自律した豊かさ」とはこういうものだ、ひいては「自律した豊かさ」の実現はこのような過程で行っていこう!と示すこと、それがプラットフォームとしてソウゾウの森会議が目指すことである。1年ずつソウゾウの森会議が積み上げていく軌跡が、少しずつこの場の価値を言語化していくのだと期待したい。


地域の数だけ存在する豊かさ
続くパネルディスカッション2は、株式会社Q0の林千晶さんがファシリテーターとなり、県外から3人のゲストを迎えてのセッション。3人を形容するキーワードはそれぞれ「森」「都市」「よそ者」。活動地域やテーマ、そこに至るまでの経歴など多岐に渡るトークから三者三様のゲストが発する秋田へのヒントに耳を傾ける時間だ。


まずは、株式会社モリアゲ代表取締役の長野麻子さん。農林水産省時代に出向先の林野庁にて木材利用課長を務め各地をめぐる中で、豊かな森を次代につなぐことを天命と感じ、早期退職。現在は事業を通じて国産木材の利用促進を行っている。さらに、森林を材料供給の場としてだけではなく多面的に捉え直し、経済や企業活動との接点をつくろうとしているところがユニークだ。例えばウェルビーイングの視点で森林をみると、その環境を活かした森林浴などのレクリエーションが企業の福利厚生になる。また、二酸化炭素排出削減の観点でみると森林は炭素吸収、木材は炭素固定に重要な存在となるなど、多様な価値を持っていることがわかる。モリアゲが実践する森と人、森と企業をつなぐ活動は一つのロールモデルであり、「森の価値変換」を掲げるソウゾウの森としても非常に参考になる取り組みである。
木々は百年、森林となれば数百年という単位で考えなくてはいけない。そうなると1人の人間、1世代では到底抱えきれない。だからこそ今のままではどうなるか、その結果が望ましくないのであればどうする必要があるか、と未来を想像し行動を起こすことが求められる。冒頭、高田先生が組織も自然も維持していくためには世代をまたいでの取り組みが必要と説いたが、森や企業からさらに広げ、地域やコミュニティの持続にも同じことが言えそうだ。

続いて、NewsPicksビジネスプロデューサーの山本雄生さんは、東京八重洲を舞台に地域経済のハブをつくるため、日本各地の地域をテーマにしたプロジェクト「POTLUCK YAESU」を展開している。そこで意識しているのは、拠点が都市だろうが地方だろうが関係なく混ざり合うことだという。また、八重洲に集まるだけでなく、東京発で地域を訪れる「移動型イベント」などを企画することで、地域に根差し活動する人材だけでなく、地域のプロデューサーとして発信していく人材を発掘したいとも語る。地域内外をつなぐ触媒となる人材がいるかいないかで、外からの地域への興味や人の流れが変わるとのこと。
様々な地域の事例を見てきた山本さんは「地域の成功は多様な形があって良いのではないか」と続ける。よく耳にする「にぎわい」という言葉ひとつとっても、3万人動員する音楽イベントを目指すのか、数百人が来場する町内の縁日が成功なのか。歴史や文化、環境を考えるとそれぞれの地域がユニークな存在であり、他所の成功事例がそのまま答えになることはないだろう。何が成功なのか、自分たちで考えていく必要があるということだ。
また、山本さんの話の中で興味深かった話をもう一つ。それは全国的にみても、大企業が地域にうまく混ざり合っている例は稀であるということ。大型ショッピングモール対商店街のような対立構造ではなく、大企業と地域が持続的な関係性をどう築くか?という視点は、秋田にも課される問いだろう。

3人目は、株式会社家守舎桃ノ音、代表取締役の上神田健太さん。岩手県出身だがパートナーの出身地である福島県国見町に移住し、現在は家業である工務店と2018年に設立した株式会社家守舎桃ノ音の2社の代表としてハード、ソフトに渡って地域活性につながる活動を行っている。
人口減少が今後も進む地域をどう豊かにするか。上神田さんは「地域資源とそこに暮らす人の個性が掛け合わさったときに唯一無二のコンテンツができる」という。例に挙げたのは運営する複合施設「Co-Learning Space アカリ」の1階にあるシチリア料理店。国見町で採れる野菜をはじめとする食材と、本場イタリアで修行したシェフの個性が出会うことでそれまでなかった、地域の特性を活かした強みが生まれたという。こうした取り組みが増えていくことで、「うちのまちはこんな町!」と市民が自信を持てるようになっていく、つまりシビックプライドが醸成されていくことを上神田さんは目指している。また、「小さい町は小さいなりに豊かであればいい」という発言は、山本さんの、地域それぞれの成功があるという話にも通じると感じた。

それぞれのゲストが秋田へのヒントを提供してくれたが、共通しているのは人とのつながりを活かすという点。計画して積み上げたというより、振り返れば点と点が繋がり、道中で出会った人やものを巻き込み、地域に合った規模で、自律的な豊かさを体現している。全国には1,724の市町村があるが、その数だけ豊かさが存在する。秋田で考えるのであれば、25市町村分の豊かさの形があるのかもしれない。いや、市町村のくくりに留まらず、集落や町内ごとにあると考えると、その単位はもっと細かく多様になっていく。

豊かさの種を拾い上げる
各回、地域の魅力や課題からテーマを設定し開催してきた今年のソウゾウの森会議。振り返ると、県内外から多様な参加者が集まることで想定していなかった出会いや発展が生まれてきた。また、外からのインプットや参加者同士の対話によって、テーマを俯瞰し、それについて考えを深める場にもなっていた。大会議の前半は、今年1年を振り返り、来年はどんな会議が行われるだろうか、ワクワクする時間だった。
秋田の魅力は、産業や自然、工芸品や祭に留まらず、個人が営む商いや生まれたばかりのプロジェクトでもあるだろう。地域に暮らす参加者がリアルに感じている「この人、この活動おもしろい!」はまだまだ表出していないと感じる。後編は「ディスカバーマップ」を使い、机の上に生まれつつある豊かさの種を見つけ、広げていく。
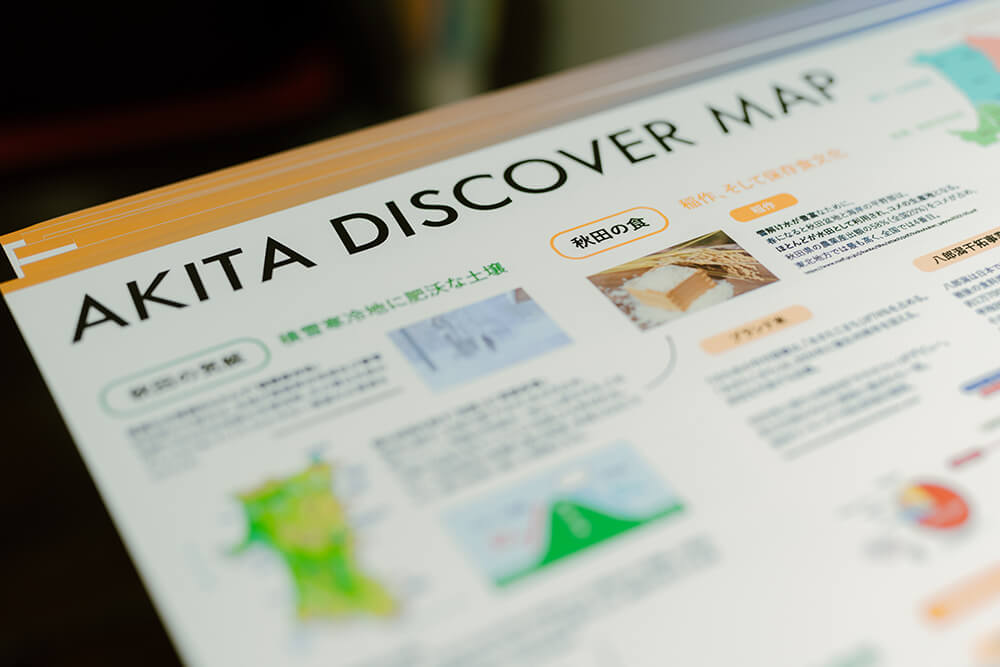
取材・文/大橋修吾 写真/星野慧 編集/加藤大雅
開催概要
【テーマ】
混ざりあう森【開催日時】
2024年11月30日(土)13:00~18:00【場所】
にぎわい交流館AU 2F 展示ホール【参加者】
86名秋田 COI-NEXT拠点 ソウゾウの森会議
主催:公立大学法人国際教養大学
共催:株式会社Q0
連携:公立大学法人秋田県立大学、公立大学法人秋田公立美術大学