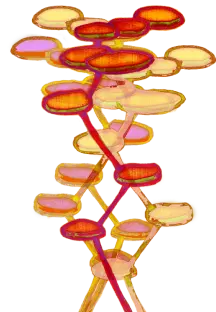ソウゾウの森大会議から早4ヶ月。待ちに待った春を迎えたものの、灯油をもう一缶買い足すか迷うほど寒さが残っている。そんな4月初週の日曜日、今年度初開催となる第17回ソウゾウの森会議が行われた。
この日は、秋田の新しいリーダーを選ぶ、秋田県知事選の投票日でもあった。集まった参加者のあいだでは、候補者のうち誰が新知事になるのかや、どんな新しい変化が起きていくのか、といった話題が話されていた。しとしと降る雨とは対照的に、会場には、秋田の将来を語り合おうというような、淡い熱気のようなものがあった。
車を降り、足で地域を歩く
豊岩地区は秋田市中心部から車で南西方面に20分ほど。雄物川が側を流れ、東には奥羽山脈を望む地域だ。佐竹県政下で推し進められた稲作一本からの脱却および高付加価値農作物の栽培にも力を入れてきた地区である。今回会場となるのは城跡が残る歴史ある地区に位置する「白華の家」。秋田公立美術大学の今中隆介先生が、木造邸宅を修復・再生し、民泊や秋田の木工作品を紹介するギャラリーのほか、学生を支援する機能も備えた複合施設となっている。


薪ストーブに暖められた室内で、会議の開始を待つ。昨年から参加している顔ぶれに加えて、一次産業従事者や子ども連れの夫婦などこれまであまり見なかった層も含めた30名弱がこの場に集まった。

まずはじめは散歩も兼ねた地域のミニツアー。道中雑談をしながら、地面から顔を出したつくしを踏まないよう畦道を進んだ先で、農事組合法人「白華の郷」の武藤真作さんから、豊岩地区の農産物について紹介がある。枝豆、大豆、蕎麦など多岐に渡る作物。特に力を入れているのが、ハウス栽培による苺だという。秋田市での大規模栽培の取り組みとしては初であり、「紅ほっぺ」や「とちおとめ」など甘くて人気の高い品種が近隣の産直施設で購入ができるそう。日照時間が太平洋側の5分の1で気温も低い秋田では、ハウスを温めたりとコストもかかるが、通年で作業があり、田植えの始まる前に収穫ができることに目をつけ、栽培し始めたとのこと。厳しい自然環境、時代の流れ、暮らす人たちの工夫。車で通れば見落としてしまいそうな見慣れた集落の風景にも、物語や個性があることを再認識した。



豊かさを決めつけない
雨にも降られ、肌寒かった集落散歩から戻ると、温かい飲み物やお茶菓子が準備されており、お互いの近況を話したり、展示された家具に触れたりと各々の過ごし方でイントロダクションの開始を待つ。
これまで県内各地で開催され、「森」を活かす地域起業家が集い、つなげ、支える場として、着実にそのネットワークへの参加者を増やしてきたソウゾウの森会議。
会議の冒頭は、国際教養大学の工藤尚悟先生から、改めてソウゾウの森会議が大事にしていることについての紹介がある。それは「秋田での暮らしの中から発想し、企てる人を地域起業家と呼ぶこと」。そして、事業性を第一に求めず、あえて起業家の前に”地域”を付けることで、風土や地域の営みから事業を発想することを表している。次に、秋田という風土の中にある「土地ごとの地域性やアクティビティを通じ、体感的に学ぶこと」。そして、地域で閉じることなく「県外、海外からゲストを招き、内と外が混ざる場をつくること」も大切にしているという。
昨年度はフィールドワークで地域を歩いたり、講演形式で先達の話を聞いたり、手を動かし皆で制作したりと、いろいろな形を試した一年であったが、その中から軸となることが明らかになった一年だったと工藤先生は語る。

続いて、今回の会場オーナーである今中先生がリーダーとなって取り組む研究開発課題4(※1)「森と技」についてのプレゼンテーション。この課題が取り組むのは「ものづくりの伝統文化を継承し、発展させる」ことだ。その中で中心的な役割を果たすのが「ORAe(秋田の方言で我が家の意)」という活動。作り手の見える、高品質で温かみを感じる家具や木工製品を展示し、実際に触れ、座り、使う機会を提供するORAeファニチャーや、言語化されず属人的になっている技をオープンにし、次世代の担い手や教育の場に受け継いでいくことを目的としているORAeエデュケーション。さらに今後は、挑戦的家具を開発するORAeフューチャーや、低価格でより子供にも親しみやすい体験を軸としたORAeファミリーを通じ、木材に関する技に触れられる裾野を広げていくとのこと。各大学、各先生の専門性と、森の価値変換という大目標の掛け合わせで生まれる可能性にワクワクが大きくなった。



自分たちで企む、ソウゾウの森会議
プレゼンテーションが終わり、いよいよ会議へ。今回は、テーマ「企む、ソウゾウの森会議」という言葉通り、会議を企画してみるという内容。具体的には、まだ主催者や地域が決まっていない第19回会議(7月開催予定)について、参加者からテーマやプログラム、ゲストのアイデアを募集するというもの。
まずは5〜6人のグループに分かれて、参加者から選ばれたファシリテーターを起点に、自己紹介の時間。ソウゾウの森会議に参加したことのある人は過去の感想を、初参加の人はソウゾウの森会議のイメージや期待していたことなどを話すことで、自然なアイスブレイクになる。自身が活動をしている人は地域や活動の内容から自己紹介することが多かったが、企業に属していたり、個人として取り組む活動がない人は、交流を通じて感じたこと、ソウゾウの森会議に求めることなどを共有した。どんな動機や状態であっても発言しやすい場になっていると感じた。


自己紹介が一周したのち、いよいよ各自でソウゾウする時間。配られたワークシートにソウゾウの森会議で行ってほしいテーマや地域・会場、参加者に投げかけたい問いなどを書いていく。子ども連れの参加が過去の会に比べ多かったのもあり、子ども世代が求める地域や環境を発表する会の開催を希望する方がいたり、三種町の名産であるじゅんさいをテーマにした会を提案する大学生。全国的に知名度の高い、大曲の花火をテーマに、参加者が実際に花火玉を製作する創作型の会を提案する会社員の方もいた。連続して参加している方がいることで、この場がどんなことを目的にしているか理解が深まってきていると感じる。また、今回が初参加となった森林の間伐事業を営む方からは、自身の事業で活用できていない間伐材や端材の利用を考える回というアイデアが挙がった。
参加者それぞれの興味や経験、アイデアがかけ合わさり今までにないテーマ、想像しなかった形式での実施が実現しそうだ。第19回の地域主催者やテーマは、この日出たアイデアをもとに事務局で検討するとのこと。最終的にどのような会議が生まれるのか、楽しみだ。




これだけ世代、仕事や学んでいることが異なる人が一つの場に集まり、地域や自身の未来について語りあう場は珍しいと感じる。わざわざ参加したくなる、他では経験できない会議になっている理由の一つに多様な背景を持つ参加者たち、というのが挙げられるだろう。
ソウゾウの森に足を踏み入れる
昨年度、年間を通しソウゾウの森会議に参加したことで、「私は特にやりたいことも決まっていないが参加していいか?」「秋田に今住んでいるわけではないが参加しても大丈夫か?」と友人・知人から聞かれることがある。地域主催者やゲストは、確たる事業を持っていたり、秋田で活動をする方が多くはあるが、参加者はそうとは限らない。
今の地域、環境、組織では何ができるか想像ができていなくとも、参加してくれている人もいる。会議後の立ち話や雑談から、ソウゾウの森会議以外でお互いに会いにいったり、別の仕事で顔を合わせ盛り上がったという話も聞く。秋田という地域で、フィールドワークや人との対話を通じ、自身のこれからについて思考を巡らせたいと思う人なら、ぜひ参加してほしい。テーマに惹かれたから、実家が近いから、友人に誘われたから、はたまた自分の活動地域に来てほしいから、どんな理由であっても、あなたが輪に参加することでソウゾウの森はまた広がっていく。

「自律した豊かさ」、それだけでは続かない?
会の最後に、共催である林千晶さんより「自律した豊かさを問うのであれば、経済性をどれくらい担保する必要があるのか?ひいては自律的な豊かさと経済性をどのように両立させられるだろう?」という問いが投げかけられる。秋田には、都会的なものさしや経済性では測りきれていない豊かさがあるのではないか、という仮説から生まれた「自律した豊かさ」という概念。3年目となる今年は「自律的に豊かでありながら、どう営みや活動を持続させるか」について、参加者と一緒に探究する一年となるのではないかと思われる。

昨年のソウゾウの森会議を経て浸透した「自律した豊かさの実現」という目標。今回新たに参加した人々のアイデアが加わり、豊かさの種や多様な生き方の可能性が広がる会になった。一方で自律した豊かさの実現に向けた取り組みを継続的に発展させていくためには、乗り越えていかなければいけない課題もある。今年度のソウゾウの森会議では、広がったテーマやアイデアをさらに深く掘り、探究していく時間が増えるだろう。ソウゾウの森会議の根っこが、より深く、力強く、地域や参加者に張り巡らされていく年となることを期待したい。

取材・文/大橋修吾 写真/星野慧 編集/加藤大雅
開催概要
【テーマ】
企む、ソウゾウの森会議【開催日時】
2025年4月6日(日)13:00~15:00【場所】
白華の家【参加者】
26名秋田 COI-NEXT拠点 ソウゾウの森会議
主催:公立大学法人国際教養大学
共催:株式会社Q0
連携:公立大学法人秋田県立大学、公立大学法人秋田公立美術大学